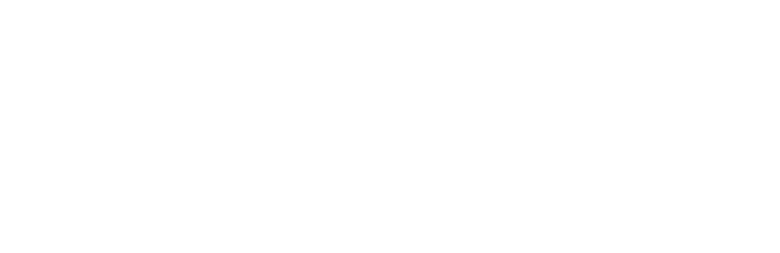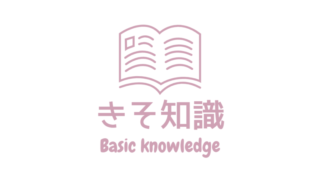住宅を新築したり購入したりする際、重要な手続きの一つに「登記」があります。
登記とは、不動産の所在地や所有者などの情報を法的に記録する手続きで、これにより不動産の権利や取引が安全に行われることが保障されます。
本記事では、住宅に関する主要な登記の種類について説明します。

家にまつわる登記一覧
表示登記
建物を新築するときに行う登記です。「表題登記」とも言います。
建物の登記記録の表題部を新しく作る登記で、建物の存在や状況を公に示すために新築建物が完成した時に行います。
建築後1ヶ月以内に行わなければならないとされており、手続きを怠ると罰則があります。
表示登記は、登録免許税の課税対象ではないため、非課税です。
一般的には土地家屋調査士に依頼します。
所有権保存登記
所有権保存登記は、登記簿に所有者の名前を入れる登記と言うと分かりやすいかもしれません。
表示登記は「不動産の物理的な状況を記録する」という意味合いを持っていますが、所有権保存登記は「不動産の所有権を他の人に主張するため」の登記です。
その建物の最初の所有者しか行わない、新築時のみの登記です。中古の場合は所有権「移転」登記となります。
一般的に「対抗力」を持つための登記ですので時間的な期限はありませんし、登記しなくても罰則はありません。
なお、所有権保存登記には登録免許税が掛かります。
土地家屋調査士が業として行うことはできず、一般的には司法書士に依頼します。
所有権移転登記
不動産の売買・相続・贈与で、所有権が別の誰かへ移転するときに行う登記です。
なお、所有権移転登記には登録免許税が掛かります。
一般的には司法書士に依頼します。
抵当権設定登記
建物などの不動産に「抵当権」をつけることを抵当権設定といい、この権利を明らかにするため行うのが抵当権設定登記です。
金融機関など「お金を貸す側」を抵当権者、「お金を借りる側」の住宅ローン借入者を抵当権設定者と言います。
抵当権設定登記は、基本的に住宅ローンの借入実行日と同日に行います。
なお、抵当権設定登記には登録免許税が掛かります。
一般的には司法書士に依頼します。
住宅ローンのように額が大きい借金の場合は不動産を担保にします。
住宅ローンを返せない事態に陥った場合など、貸したお金が返ってこないときに、不動産を売って回収できる権利を抵当権といいます。
分筆登記
一筆の土地を分割して、複数の土地にすることを分筆登記と言います。
分筆しても権利関係は変わりませんので、登記簿には元の土地の権利関係を転写することになります。
申請には地積測量図の添付が必要で、その地積測量図を作成するための境界確定には隣地所有者の立ち合い確認が必要だったりしますので、手間と時間が掛かります。
一般的には土地家屋調査士に依頼します。
地目変更登記
地目を変更する際に行う登記です。例えば、現在「畑」となっている地目を「宅地」へ変える場合などです。
地目に変更が生じた日から一ヶ月以内に行わなければならないと定められており、手続きを怠ると罰則があります。
一般的には土地家屋調査士に依頼します。
滅失登記
現在ある登記簿を滅失させるための登記です。
解体等により建物が無くなったときに行う登記です。
解体後一ヶ月以内に行わなければならないと定められており、手続きを怠ると罰則があります。
滅失登記には登録免許税は掛かりません。
一般的には土地家屋調査士に依頼します。
司法書士と土地家屋調査士
住宅における登記には、司法書士と土地家屋調査士がそれぞれ異なる役割を担当しています。
登記情報は、所在地、面積などの「表題部」と、所有者、抵当権者などの「権利部」で構成されており、表題部を登録するのが土地家屋調査士の仕事、権利部を登録するのが司法書士の仕事です。
司法書士会連合会 https://www.shiho-shoshi.or.jp/
土地家屋調査士会連合会 https://www.chosashi.or.jp/

今回は「登記」に関する記事でした。
たまに「表示登記は自分でやって費用を削減しよう」と考えている方がいますが、おすすめしません。餅は餅屋です。プロに任せたほうが良いですよ。
筆者:ともぴ(一級建築士/インテリアコーディネーター)
「家づくりは、賢く・楽しく・ちょっとあざとく」をモットーに、失敗しない家づくりのヒントをブログで発信中。