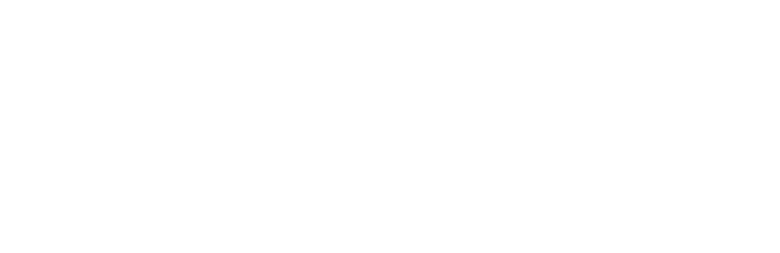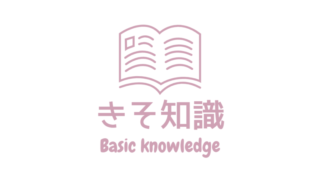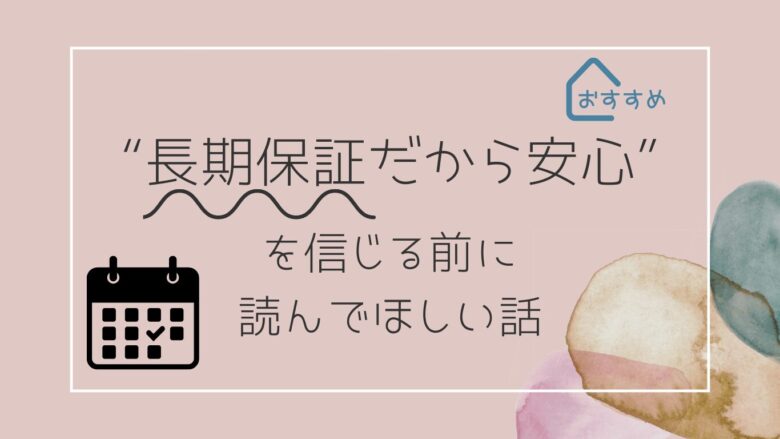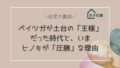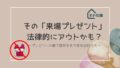家を建てるとき、住宅会社の営業担当から「うちは30年長期保証付きだから安心ですよ!」なんて言われると、ちょっと安心しますよね。
でもその“安心”、中身をよく確認しないと、後から「えっ?そうなの?」となる可能性があります。
本記事では、住宅業界の裏側も交えながら、「長期保証」の仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
前提:「10年保証」は法律で義務

新築住宅は、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に関して、10年間の保証を義務付けられています。
これは「住宅瑕疵担保履行法」という法律に基づくもので、住宅会社の善意ではありません。全ての住宅会社が守るべきルールです。
つまり、「10年保証付きです!」というだけでは、特別なサービスではなく最低限のラインです。
「30年保証」「60年保証」はマーケティング戦略です

10年を超える保証、いわゆる「長期保証」は住宅会社が独自に設けている任意の制度です。
これは法律で義務づけられたものではなく、マーケティング戦略の一部であることがほとんどだと思ってください。
もちろん、その制度が悪いというわけでは決してありません。ただ、慈善事業ではなくビジネスとして成り立つ仕組みである、という前提は理解しておくべき点です。
混同されがちですが、「長期優良住宅」と「長期保証」はまったく別物です。
長期優良住宅は、住宅会社ではなく施主自身が自治体から認定を受ける制度。「長期優良住宅」としてあり続けるには、住まい手自身が維持管理計画を立て、実行していく必要があります。
つまり、「長期優良住宅=手間いらずで一生安心」ではありません。
有償メンテナンスありきの延長保証

長期保証を維持するには、定期的な点検に加えて、住宅会社が指定する有償メンテナンスを受けることが絶対条件です。
しかも、そのメンテナンスを別の会社で行った場合は保証が打ち切りになるケースがほとんどです。
「うちでメンテナンスをしないと、保証は終了しますよ」
というのが実態というわけです。つまりこれは、ある意味住宅会社に足元を見られる仕組みとも言えるでしょう。
ケーススタディ:外壁サイディングのメンテナンス
最近のサイディング外壁は耐久性が向上しており、10年でボロボロになるケースは稀です。
にもかかわらず、保証の延長条件として「10年目に外壁塗装を必ず実施」などが設けられていることがあります。
「まだ綺麗だし、劣化もしていないのに…」と思いながらも、保証を維持したいがために数十万円の出費。これは一種の“保証料”とも言えます。
もちろん、早めのメンテナンスが無駄とは言いません。けれど「今、本当に必要?」と悩む方も多いのが現実です。
とはいえ、“売りっぱなし”の会社より、ずっとマシ

ここまで読むと、「じゃあ長期保証ってダメなの?」「長期保証サービスってウソじゃん」と思うかもしれませんが、そうではありません。
確かに、保証制度の裏にはビジネスの仕組みがありますが、それでも将来の維持管理まで事業として考えている住宅会社は一定の評価に値します。というか、めちゃくちゃ偉いです。
何の仕組みもなく売りっぱなしにする会社より、ずっとマシです。これは現場を見てきたからこそ、声を大にして言いたいことです。
ただ、どれだけ立派な保証制度が用意されていても、住宅会社が倒産してしまえば元も子もありません。とくに長期間にわたる保証制度ほど、制度そのものよりも会社の継続性や財務基盤の確認のほうが重要になってきます。
大手メーカーの安心感が遺憾なく発揮されるのは、新築時ではなくアフターメンテナンスのタイミングというわけなんですよ。
本当に良い保証制度とは?

理想的な保証制度とは、その家の仕様や立地・環境に応じて、適切な時期にメンテナンスを行い、それによって保証が延長されるような仕組みです。
ですが、住宅会社側にとって個別対応の管理コストが大きいですし現実的ではありませんので、画一的な保証条件(10年ごと等)に落ち着いてしまっている住宅会社が多いです。
まとめ|家を守るのは「住まい手の主体性」

長期保証制度は、使い方を間違えなければ有効な仕組みです。
しかし、「長期保証があるから安心」「長期優良住宅だから大丈夫」と思考停止してしまうのは危険。
家を守るのは、制度でも会社でもなく、最終的には住まい手の主体性なのですよ。
仕組みの背景を理解し、費用対効果を見極め、賢く選択する。
これこそが、将来後悔しない家づくりに欠かせない視点だと思います。
筆者:ともぴ(一級建築士/インテリアコーディネーター)
「家づくりは、賢く・楽しく・ちょっとあざとく」をモットーに、失敗しない家づくりのヒントをブログで発信中。